深夜。
いくつもの人影が走り、サイレンと車両が急ブレーキをかける音がいくつも響く。
元々、ここまで大仰な事態にはしたくなかった。
彼らは犯罪者だが、その素性が表に出れば世間に混乱を巻き起こすことは必至。
この件は秘密裏に処理しておきたいのだ。
「やぁ、遅かったですね。既に包囲しましたよ」
制帽を被った男が笑いながら近づいてきた。
この男に全く悪意が無いのは分かっているが、彼が事の重大さを全く理解していないのもまた事実だ。
「どうも。残りは僕達に任せてもらおう」
「隊長が出る必要はないでしょう? もうすぐ俺の部下がそのハッカーを連行してきますよ。コーヒーでも飲みます?」
「いや、遠慮しておくよ。こっちも仕事でね」
足早にその場を離れる。
背後でわざとこちらに聞こえるように不満を呟く声が聞こえたが、無視した。
警報が伝わってからわずか数分後には、建物は十数台のパトカーや特殊車両に囲まれていた。
ここが政府管理の建物であることは分かっているが、作業時間すらろくに用意できないのは想定外だった。
警察の特殊部隊と思われるフル装備の隊員が数名侵入してくるのが見えた。
「おい、まだか!」
「見れば分かるでしょ! 全っ然時間が足りない!」
外部から侵入してのハッキングは難しい。
部屋の外から響く、いくつもの足音が焦燥感を駆り立てる。
やむを得ない。
「時間を稼いでくる。逃げる準備をしてくれ」
「どうする気?」
「寝ててもらう」
「えっ、私?」
「いやお前じゃなくて……頬赤らめてんじゃねぇよ!」
そんなやり取りをしている間にも、扉が乱暴に開けられ、数人の警官が部屋に突入してくる。
彼らは銃を構え、内一人が「動くな!」「手を挙げろ」と叫んだ。
刑事ドラマみたいな台詞には多少呆れる。
懐中電灯の光が自分達を照らす。
「どいてくれ」
左手をポケットに突っ込み、この状況では欠かせない道具を取り出した。
輝きが懐中電灯の光を圧倒する。
引き金を引こうとした瞬間、装甲の付いた腕が警官達をまとめて弾き飛ばした。
ガシャガシャという音を響かせながら、階段を駆け上がる。
屋上へ出ると、屋根から屋根へ飛び移り、更に走る。
息が上がりそうになるが、休んでいる場合ではない。
「私達だけで出来る仕事じゃなかった!」
「クロスハートに連絡しろ! 作戦は失敗だ!」
「私が? 失敗の報告なんて嫌よ、あんたがしなさいよ! このアイデア出したのはあんたでしょ!」
「お前……伏せろ!」
言い返そうとした瞬間、目の前にいくつも積まれた木箱が一瞬にしてばらばらになり、破片が降り注いだ。
これは牽制だ。
粉塵が収まるとすぐに立ち上がり、正面を見つめる。
敵は警官隊の残りではないかと思ったが、それは違った。
そこにいたのは二人だけ──正確には、一人と一体だけだった。
この二人のことはよく知っている。
「わざわざあんた達のお出ましとは」
「政府直轄のこのビルを狙うのは君らくらいだろう」
金髪の長身、精悍な顔つき。
自分よりもいくつか年上、おそらくもう40歳に近いはずなのに、驚くほど整った見た目だ。
こういう存在を見ると、世の中とは不公平なものだと実感せざるを得ない。
トーマ・H・ノルシュタイン、DATS日本支部隊長。
実際に姿を見るのは初めてだ。
彼の、青い装甲に紅いマントを羽織った獣騎士型のパートナーが、巨大な刃を備えた右腕をこちらへ向けてくる。
「どうか抵抗しないで欲しい。僕としては、君達を傷つけたいとも、罪をより重くしたいとも思わない」
「あぁ、そう」
取り出したデジヴァイスを見て、トーマの表情が曇った。
これから起こることを想像してか。
だが、こちらも彼の思惑通りの展開にするつもりはない。
「マスター、戦闘の許可を」
獣騎士の言葉に、トーマは手を上げて制する。
まだ交渉を続けたいらしい。
「判断が早いな。もう少し考える時間を与えても良いんだが?」
「別にいらないさ」
「どうしても戦う気かい」
「黙って捕まるよりは、怪我する方がマシなんでね!」
手のひらを掲げる。
白く輝くコードが現れ、それをデジヴァイスでスキャンし──輝きに包まれながら、神原拓也は叫んだ。
「スピリット・エボリューション!!」
突如、闇に巨大な火の玉が燃え上がり、更にその中から炎の十闘士が現れる。
神原拓也──スピリットに選ばれし者は、データの装甲を纏い、今や炎の十闘士・アグニモンへと進化していた。
跳びあがりながら上体を捻り、拳に渾身の炎の力を籠め、右腕を振り上げる。
狙いは青い獣騎士型のデジモン・ミラージュガオガモン。
「サラマンダーブレイク!!」
凄まじい光を放ちながら振るわれた炎の拳は、しかし目標には当たらなかった。
直前までトーマの隣に居たはずのデジモンは一瞬にして眼前から消え去り、業火が爆散する。
視界には獣騎士はいない。
だが月光によって発生する影が、敵の居場所を分かりやすく示していた。
宙に跳んだミラージュガオモンはアグニモンめがけて落下している。
それに気づいた瞬間、彼は後方へ一回転し距離を取る。
そしてズン、という音と振動を感じると、再び拳を繰り出した。
その拳は空を切ったが、しかし今度は獣騎士が身体を捻って避け、バランスが崩れていることを見て取った。
アグニモンは次の攻撃が命中することを確信し、一回、二回と拳を繰り出す。
更に足に炎を溜め込み、次の攻撃の準備を怠らない。
右足を踏み込むと同時、ほぼ零距離からの炎の旋風脚・サラマンダーブレイクを放った。
攻撃後、自分の左足の先に、ミラージュガオガモンは直立していた。
「遅いな」
「速っ……」
ガァン、という音と共に、脳に凄まじい衝撃が伝わる。
巨大な爪の装備された拳で顔面を殴られたことに気づくのはやや時間が掛かった。
ツキノワグマに生身で殴られた時はこんな気分を味わえるのかもしれない。
更に腹部を蹴られ、肺の中の酸素をあらかた絞り出される。
衝撃に忠実に、身体が後方に飛ばされているにも関わらず、獣騎士がグングン近づいているのは不思議で仕方がなかった。
「ゲイルクロー!」
巨大な爪が身体を裂いていくのが、妙にスローで見えた。
意識がまだ残っていることは感謝すべきか否か、血塗れになった自分の身体が横たわっているのを感じた。
それと、誰かが近くにいるのも。
「すまないが、逮捕させてもらう。聞きたいことが山ほどあるのでね。安心してくれ、答え方によっては減刑もあり得る。チャンスと考えて、どうか我々に協力してほしい」
ぼやけた視界の隅に、DATS隊長の姿が映っていた。
無表情に言葉を述べるその姿を見た時、ねばねばした液体でぼうっとした頭の中をかき回されたような気がした。
だが自分は炎の十闘士だ。
この液体は燃料になる。
感情の業火だ。
「ふざけるなよ」
「何?」
「デジモンを裏切ったお前達に、協力なんかするか」
頭髪を握る獣騎士の瞳に、再び殺意が宿ったのが見て取れた。
突然、風が吹き荒れたかと思うと、身体が宙に浮き(そして頭皮に若干の痛みを感じ)、自分の視界からトーマとミラージュガオガモンが急速に遠ざかった。
ついさっきまで睨み合っていた二人が、今度は唖然とした表情を浮かべているのも当然だろう。
理由は解りきっている。問題はタイミングだ。
「おい、シューツモン!何すんだよ!」
ついさっきまで身を隠していた相棒・織本泉は、何時の間にか風のビーストスピリットの力によって進化し、アグニモンを羽交い絞めにして宙へと飛び去っていた。
「逃げるのよ! それ以外にある?」
「戦うところだろ今は! 降ろせ、あと手伝え!」
「却下よ! この戦いに意味はない!」
「クロスファイアーなら奴らを倒せる!」
「アグニモン、私達のやることは何!? 小競り合いで優越感を得ること?」
この言葉は最もアグニモンに効果を上げた。
彼の怒りのガソリンによって燃え上がった炎が、急速に鎮火していくのをシューツモンは感じた。
悪態をつきながらも、アグニモンは抵抗を止め、彼女に従った。
瓦礫と火の粉がそこら中に散乱した屋上で、トーマは小さくなっていくシューツモンの影を見つめていた。
ミラージュガオガモンの退化した姿──成長期の青い獣型デジモン、ガオモンが、彼の主に問う。
「追わなくて良いのですか」
「相手があれでは、徒労に終わるだろう」
それに、とトーマは付け加える。
彼もまた、アグニモンやシューツモンと同じことを考えていた。
「我々が狙うのは大物だ」
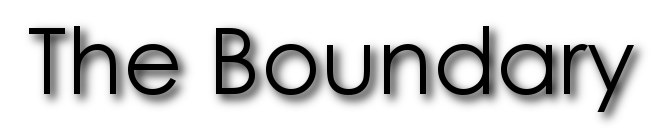 【The Boundary】
【The Boundary】
1/Side:Black“時代は変わる”
【トーキョー・ウィーク電子版 7月23日号】
『ウバフ政権転覆、なおも混乱収まらず』
現地時間7月22日未明、ロリシカ共和国の市民革命軍≪聖なる都≫は大統領官邸を占拠、ウバフ大統領を拘束したと発表した。死傷者の人数は不明だが、民間人を含め300人を超えるとの見方がされている。二年前の政権交代から、強引な政治手法で管理国家を目指してきたウバフ政権へ、国民の怒りが爆発した。ロリシカ共和国では、議会で一ヶ月前に新たなデジモン管理法案が通過したばかり。全世界的に進められるデジモン管理の法案整備に対し、ロリシカ国民は断固拒否の姿勢を示した。(続く)
「だから何度も言わせるな、ウチの記者はちゃんと帰れるのかと聞いている! 特ダネ掴んだ大事な記者なんだ、死なせたらあんたらの責任になるんだぞ!」
同僚が電話口へ怒鳴る声を聞きながら、佐倉一人(かずと)は自分のデスクへ座った。
ロリシカ共和国のクーデターから一夜明けても、トーキョー・ウィーク本社の電話はまだ鳴り止まなかった。
取材レポートと写真の画像データがひっきりなしに届き、メールボックスはあっという間に未読で埋め尽くされる。
さてどうしたものか、とどこか他人事のように考えながら、一人は隣に座る同僚が叩きつけるように電話を切るのを見て顔をしかめた。
「そう怒鳴るな、敬(けい)。大使館だって何もしてない訳じゃあるまいし」
「好きでキレてる訳じゃねぇよ。公務員ってのはどうしてこんな紋切型の回答が好きなんだ?」
「奴らもしばらくしたら出版部の餌食になるさ」
「確かに。かわいそうにな」
「少し休むべきじゃないか。何時間そこに座ってるんだ」
「ん、そうか……そうだな、ちょっと失礼させてもらうよ」
立ち上がる敬を尻目に、一人はメールボックスのタイトルだけチェックすると、机に雑然と散らばる紙資料をファイルに突っ込み、パソコンの電源を落とした。
その様子と自分の腕時計を見比べながら、敬が問いかける。
「取材か?」
「あぁ、悪いな。行ってくる」
「どこへ」
「この前から抱えてるアレだよ。やっと直接アポが取れた」
「この前……あ、え、マジかそれ」
「嘘ついてもしょうがないだろ」
一人は腰を上げ、同僚に向き合った。
「本宮大輔に会いに行ってくる」
世界は変わった。
20世紀の終わり、人類はデジタルモンスターと出会った。
記録される限り、1995年の東京で目撃された、二体のデジモンの戦いが最初だ。
ごく初期は子供達だけがそれに関わっていた。
それもこの世界とは別の世界、デジタルワールドに行く権利を得た一握りの子供達だけだ。
戦いが大きくなり、デジタルワールドだけでは収まらなくなったことで、それは子供だけの問題ではなくなった。
いくつもの戦いと、勝利と、挫折を経て、今の世界がある。
人類の多くがパートナーデジモンを持ち、それが当たり前となった世界。
デジタルワールドが身近になり、宇宙開発も進む世界。
20世紀の終わりから見れば、この世界は理想郷なのだろう。
だが現実は違う。
最初は食糧問題だった。
元々、20世紀の終わりの頃には既に、深刻な食糧危機が人類共通の問題として横たわっていた。
21世紀になり、デジモンのパートナーを持つ人間が爆発的に増えたことで、すぐに食べるものに困らない国は無くなった。
デジタルワールドにも食糧はあるのか? 当然だ。
だがデジタルワールドからの供給を含めても、需要はそれを遥かに上回っていた。
それまでが問題にならないほどの、絶大な貧富の差が生まれた。
次に紛争と戦争。
飛行機はライト兄弟が初飛行に成功してから僅か10年余りで戦争の道具になった。
アインシュタインが特殊相対性理論を発表してから約40年後、戦争で原子爆弾が使われた。
デジモンも同じだった。
少なくとも生身の戦闘能力が人間を上回り、場合によっては一体で一個小隊にも匹敵する力を持つ知能を持った生き物を世界が見逃すはずが無かった。
まず紛争地域で、それから先進国の軍隊で、デジモンが軍事行動のために使われた。
そして最も深刻なのが権利問題。
人類はこれまで、言語を理解できるほどの知能を持つ生き物を自分達以外に知らなかった。
全ての国の憲法や法律は、人間のために作られたものだった。
国による差こそあれ、デジモンは人間と同等の権利を得られなかった。
多くの人間にとってデジモンはペットであり、家畜であり、奴隷だった。
そのオフィスに入るためには、国際線搭乗並みの厳重な検査を通過する必要があり、彼に会うまでには既に取材の約束の時間を10分ほど超過していた。
東京の一等地、巨大オフィスの最上階。
白い電波塔が良く見える見晴らしの良い応接間に一人は立っていた。
「佐倉一人です」
「あんたが? 本宮大輔だ、よろしくな」
実際に見た彼の姿はイメージよりもややガタイが良く、噂通りの豪快な雰囲気の人物だった。
本宮大輔、僅か36歳にしてモトミヤホールディングスのCEOを務める男。
かつて世界を救った英雄のひとりでもある。
彼がアメリカで始めた外食産業は大いに成功し、数年後には日本をはじめとする世界中へ進出した。
デジモンを他のどの企業よりも優遇して雇用し、2020年代中盤には世界最大規模の企業へと成長、様々な業界へ進出し多くの企業を吸収合併した。
食品から軍事製品まで、モトミヤグループが手を出していない業界はない、とまで言われている。
そのトップに立つ本宮大輔は、日本経済を立て直した男と言っても過言ではないのだ。
既に実質的な経営は後続に任せているというが、政財界への影響力は未だに健在。
そんな彼への直接のインタビューを取るのは、それなりの苦労と時間を要した。
「ダイスケー、時間大丈夫なの?」
「いいんだよブイモン、その辺は我が社が誇る敏腕秘書が上手くやってくれっから」
小さな青い竜型デジモンが大輔の近くへやってきた。
「初めまして、ブイモン。まさかあなたにも会えるとは」
「まーねー、雑誌的にはオレの写真も欲しいんでしょ?」
「そういうことです」
今やモトミヤホールディングスのマスコットと化しているブイモンだが、彼も本来は大輔のパートナーデジモン。
彼がかつて世界規模の脅威から人類を救ったという事実はあまりにも有名で、これは大輔の会社を成長させることにも大いに役立った。
彼が「ブイモン専務」として出ているCMを知らない小学生は多分いないだろう。
大輔が本来の話題に戻す。
「で、どんなコメントが欲しいんだ?」
「読者ウケの良いコメントを」
「あぁ、つまり、溶岩風爆熱ラーメンの開発秘話?」
「もっと下世話な話でいいんですよ。例えば、昨年あなたが行った巨額の政治献金の話とか」
一人は若干の冷笑を含んだ──だが、はっきりとした口調で──大輔に聞いた。
ブイモンの動きが一瞬ピタリと止まったが、大輔は笑みを見せながらも、動揺した様子は見えなかった。
「随分と単刀直入なんだな」
「そういう雑誌なので。あなたも分かっているでしょう」
「困ったな、会社の取材だと思ったんだが」
冷茶を口に運んでから、軽い調子のまま大輔は続ける。
「献金はあくまで俺個人でやったことだし、会社は関係ない。もちろん社員の政治思想も一切関係なし。以上でいいか?」
「では、あなた個人としてはどういうお考えで?」
「どれについてかな?」
「デジモン管理法案についてですよ」
ここまで全く動揺を見せていない大輔に、一人は更に直接的な質問を浴びせかけた。
正直、少しくらいは言いよどむ場面があるだろうと考えていただけに、この流れはかなり意外だ。
ならば、彼の意見をそのまま聞くまでだ。
「今審議されているデジモン管理法案。もし可決されれば、デジモン先進国とまで言われた日本国内でのデジモンの立場は大きく変わるでしょう。そしてあなたは日本最大の企業のトップだ。企業だろうが一個人だろうが、あなたが動けばデジモン全体に影響が及ぶのは容易に想像がつく」
「あぁ、うん」
「正直、驚いてるんですよ。あなたはかつてリアルワールドとデジモン、両方を救ったヒーローだ」
「そのヒーローがデジモンを縛る法案に賛成している、ってことだろ?」
先に持論の結末を言われ、一人は言葉を切って頷いた。
「そう思われるのは無理ないよな、ブイモン」
「まぁ、そうだよね」
ブイモンは大輔に比べ固い表情を浮かべながら頷いた。
パートナーとの間に確執があるのかとも思えたが、そうではないことはすぐに分かった。
ブイモンが一人に聞く。
「カズトさん、グレートキャニオン虐待事件を知ってる?」
「え? あ、あぁ」
思わぬタイミングで質問を返され、思わず頷いた。
グレートキャニオン虐待事件。
2年前、デジタルワールドの居住区問題をめぐって、民間の再開発企業とデジモン達との間で抗争が起きた。
多数の逮捕者が出たが、問題はその後だった。
逮捕されたデジモン達への虐待映像がネットを中心に出回り、デジモン保護団体の政府への抗議が殺到。
一方でデジモンの存在を危険視する人間達によるデジモン排斥運動も活発化すると同時に、面白半分にデジモンを虐待する人間も急増した。
以後デジモンを人間社会のなかでどう扱うべきか、権利と自由をどう守るべきかの議論が今なお続いている。
「あの事件の後すぐにブイモンとグレートキャニオンへ行ったんだ。正直、何年もデジタルワールドに行ってなかったが、アレで目が覚めたよ。いくつか集落を回ったが、あんなに冷たい目で見られた経験は25年前でも無かった」
「……」
「今の世界情勢で、デジモンを守れる場所は法の下しかない。それが俺の結論だ。そのためなら金も地位も何だって使うさ」
この言葉を呟いている彼の目には鋭い光が宿っているように見えた。
この、冗談めかした言葉ばかり吐いていた男の心の底にあるものを、一人は初めて知った気がした。
「あぁ、ちなみに」
「はい?」
「一人さん、そういうあんたは管理法案をどう思ってるんだ? 記者としてではなく、一個人として」
「……私には正直、どちらでも良いことですね」
ほんの一瞬、一人の言葉が詰まったことに大輔が気づかないはずは無かったが、彼は頷くだけで、それについての追及は何もなかった。
「私にはパートナーがいないので」
「なるほど、そういうのも沢山いるからな。うん。で、他にまだ聞きたいことは?」
その後は大輔の饒舌なトークが続き、取材は滞りなく終了した。
序盤の緊張感はどこへやら、彼は随分と一人のことを気に入ったようで、おそらく記事の材料にはならないであろう過去の冒険の話(自分と結ばれる運命だった女の子がいた、とか)もうんざりするほど聞かされた。
写真撮影も終えオフィスを出れば、そこには目の前に黒塗りの高級車が止まっており、黒スーツの女性がにこやかな表情で乗車を促してきた。
「お送り致します」
サービスの良さに多少面食らいながらも、言われるがまま後部座席に乗り込む。
丁寧にドアを閉め一礼する女性に会釈しながら、落ち着かない表情を浮かべた一人を乗せて車は発進した。
スーツの女性が出発してすぐにどこかへ電話していることに気づく余裕は無かった。
「起きなさい」
頭や腰、それに背中に酷い痛みを感じながら、一人は目を覚ました。
周囲は暗く、冷たそうなコンクリートで覆われており、外の明かりは見えない。
見覚えのない場所だ。
そしてパイプ椅子に座らされ、両腕ごと身体も縛りつけられていることも、一人には全く覚えが無かった。
これは問題だ。
「おい、起きろっつってんだ」
男の声。
さっきとは別の声だ。
一人はのろのろと辺りを見回した。
左右に二人の男が立ち、それぞれ傍らにデジモンを従えている。
右腕を上げこれ見よがしにミサイルを構えるマシーン型デジモンと、クリオネのような姿の小さなデジモンだ。
そして一人の正面には、白衣を着た女性と、黄色い戦闘機の形をしたデジモン。
ぼんやりした頭がようやく状況を飲み込み、一人はため息をついた。
「悪いんだが、人違いだな。俺はモトミヤ社の社員じゃないんだ」
「それは分かってる。あんた、トーキョー・ウィークの記者だろ」
右側に立つ茶髪の男が言う。
捕まってから素性が割れたのか、それとも予め知っていたのか。
「なら、俺が仕事中なのも分かるよな。早く会社に戻って原稿を仕上げなきゃならないんだ。送ってくれるって聞いたから車に乗ったんだが、道を教えればいいのか?」
「どこに送るかまでは言ってなかったわね。ごめんなさい、勘違いさせてしまったかしら」
黄色いデジモンを従えた女性がゆっくりと一人に近づいてきた。
顔をじっくりと眺めて、ようやく気づく。
彼女、今は白衣だが、さっきの黒スーツの女だ。
「縄はすぐ解くわ。私達の言うことに従ってくれたらね」
「この状態で何に従えって言うんだ。そういう性癖の奴向けのビデオでも撮るのか?」
黄色いデジモンは露骨に嫌悪感を浮かべて女の方を見る。
当然だ、こんな奴らに言われるがまま従って気分が良いはずがない。
少しくらいこちらの気持ちも汲んでほしい。
「ねぇネネ、こいつムカつくよ。壊してやりたい」
「最初に駄目って言ったでしょ、スパロウモン」
女は膝を曲げ、視線を一人と同じ高さに合わせた。
若干胸元が見えるのが嬉しいが、黙っておこう。
「トーキョー・ウィーク記者、佐倉一人くん。私のお願いはただひとつよ。本宮大輔のところにもう一度行って、軍事部門の新兵器設計図を拝借してきて」
「……は?」
この言葉を理解するには少々時間が必要だった。
あまりにも突飛な、それこそさっきのビデオ撮影よりもはるかに馬鹿げた話だ。
一人はこの言葉が冗談であることを信じながら周囲を見渡したが、残念ながらそこにいる全員が(さっきまで穏やかな表情だったクリオネ型の天使も含めて)、彼を硬い表情で見つめていた。
「そんなの無理だ、無理無理! 頭おかしいのか!?」
「悪いがこっちは真剣なんだよ、佐倉さん。取材という名目であそこに入れる人間の力が借りたい」
「簡単に言いやがって、そんな……」
「簡単じゃないのは知ってるわ。私達も簡単じゃないことをしてるから」
「監禁の仕事が? それともAV撮影か?」
「ねぇネネ、こいつ壊」
「黙って」
白衣の女が溜め息をつく。
納得いかない、全く納得がいかない。
今度ははっきりと怒気を含んだ声で、一人は言った。
「仕事頼みたいなら、まず身分を示せよ! 何者なんだあんたら!?」
「私は天野ネネ。隣のこのコはスパロウモン。それから──」
「塩田博和だ。それと、ガードロモン」
「僕は北川健太。こっちはマリンエンジェモンだ」
「無茶なことをお願いしてるのは重々承知よ。私達はクロスハート。あなたも記者なら、名前を聞いたことないかしら」
「クロス……ハート……!? って、まさか……あの? 情報省ハッキング事件の、あのクロスハートか!?」
「知ってるのなら結構」
合点がいった。
何故なら彼らは、一人が取材で何年も追っている者達だからだ。
比較的近い人間にも何人か出会ったことがあるが、実際に所属している人間とデジモンに会うのは初めてだった。
デジモン保護団体にして国際的テロリスト、クロスハート。
雑誌の記事に目を通していたのなら、彼らが一人の名前を知っていることも合点がいく。
「言うなれば、これは取引よ。あなたが私達の仕事を引き受けてくれるなら、私達もあなたの雑誌の餌になってあげるわ」
一人は顔を伏せたが、ネネは構わなかった。
「もちろん、全ての事が済んでからだけれど。長期的に考えれば、あなたにも利益があるはず」
眼鏡の男・北川健太が、彼女の言葉に続く。
「ウチも人手不足で、しかも時間が無いんだ」
「ぴぴぃ」
「強引なやり方で頼んでいるのは本当に申し訳ない、謝るよ。その上で、どうか、あなたの力が借りたいんだ」
一人は暫く黙って、考えていた。
と言うより、正確には、考えている様子を見せ、彼らを観察しているだけだった。
答えは決まっているからだ。
これほど美味そうな飯の種は無い。
一人は頭を上げ、ネネに言った。
「その話、乗ろう。やってやるよ」
「……そう。ありがとう、一人くん」
「ところで、まず知りたいんだが。軍事機密なんか調べてどうするつもりなんだ?」
「勝つためよ」
「勝つ……?」
「えぇ」
「誰に?」
「国に」
今一つ納得のいかない表情を浮かべる一人に、ネネは行き過ぎなほど顔を近づけ、静かに言った。
「今の政府を潰すためよ、一人くん」
|